徳川家康といえば「狸親父」ですが、実は見た目だけが理由で付けられていません。
今回は、家康の人物像を紐解きながら、知られざるあだ名の世界へお連れします。
- 徳川家康のあだ名は「狸親父」?
- 「狸親父」だった理由は見た目?
- 現代での「狸」の意味とは?
- 他の武将からの呼ばれ方
- 徳川家康の幼名の変遷
- 徳川家康の他のあだ名一覧
- 徳川家の他のあだ名一覧
徳川家康のあだ名は「狸親父」?

徳川家康の最も有名なあだ名は「狸親父」ですが、実は複数の呼び名があります。あだ名から家康の善悪だけでは割り切れない複雑な人物像を知ることが可能です。
まず「狸親父」というあだ名は、家康の敵対勢力から生まれたとされています。戦国時代は裏切りや同盟の切り替えが当たり前でしたが、家康は特に慎重かつ計算高く立ち回りました。
敵対する武将たちから見ると、「家康は狸のようにどっしり構えて、油断も隙もない」という印象だったようです。悪口というよりも、家康への畏怖が込められていたと考えられます。
家康の死後は、「東照大権現」という全く異なるあだ名が生まれました。家康を神として祀った際の神号で、江戸幕府の権威を高める政治的意図があったようです。
「東照」は「日本の東方を照らす」という意味で、徳川の天下を照らす存在として家康を位置づけています。日光東照宮の豪華な社殿は、神格化された家康への崇拝を現代まで伝えているわけです。
「狸親父」と呼ばれていた理由は見た目?

徳川家康が「狸親父」と呼ばれた理由は外見もありますが、それ以上に家康の政治的戦略が大きく影響しています。外見だけでなく、行動が「狸」のイメージと重なったわけです。
「狸」の由来1
肖像画を見ると、織田信長や豊臣秀吉と比べて、家康はふくよかに見えます。家康の肥満体型が、狸の丸いフォルムと結びついたのは自然です。
家康は晩年になるにつれて、どんどん太った体型になっていきました。野生の狸も全体的に丸みを帯びていたため、家康の外見と重なって見えたのかもしれません。
家康本人も自分の体型を使い、農夫の格好で周りを笑わせることがあったといわれています。家康のお笑いセンスも、狸親父のイメージに影響を与えた可能性が高いです。
「狸」の由来2
家康の「狸」的な性格は、幼少期の経験に根ざしています。
家康は若い頃から今川家や織田家の人質として生活を送っていました。人質経験が、周りの大人の顔色を窺いながら生きる慎重さを育てたのです。
人質として過ごした年月により、家康は外面の良さと内面の計算高さを同時に身につけました。表面的には従順に見えながら、内心では状況を冷静に分析するという二面性こそが「狸」のイメージと重なります。
三方ヶ原の戦いで武田信玄に大敗した家康は、自分の敗走する姿を絵に描かせ、戒めとしたという有名な逸話も、家康の慎重さを強く印象づけるものです。
「親父」の由来
「狸親父」の「親父」部分は、家康が高齢で天下統一を成し遂げたことと関係しています。織田信長が天下を目前に本能寺で倒れたのが48歳、豊臣秀吉が日本を統一したのが54歳でした。
一方、徳川家康が大坂夏の陣で豊臣秀頼を滅ぼし、完全な天下統一を果たしたのは73歳の時です。70代は、当時の感覚でもかなりのお年寄りでした。
特に大坂の陣では、73歳の家康が22歳の豊臣秀頼と対峙する構図となりました。老人が世間知らずの若者を巧妙に追い詰めていく様子は、まさに「狸親父」のイメージそのものです。
徳川家康自身は「狸親父」をどう思っていた?
「狸親父」という呼び名ですが、家康本人は自分の「狸」イメージをむしろ活用していた可能性が高いです。戦国時代を生き抜いた家康の、意外な一面を見ていきましょう。
家康は「狸親父」を否定しなかった
歴史的な記録を見ると、家康が「狸親父」という呼び名を嫌がった形跡はありません。むしろ、ずる賢いイメージを戦略的に利用していたようです。
家康は自分のふくよかな体型を使って、周囲を笑わせることがありました。農民の格好をして家臣たちの前に現れ、場を和ませたという逸話も残っています。
敵対勢力から恐れられる存在であることは、戦国大名にとって有利に働きます。「油断できない相手」という評判は、戦わずして勝つための武器でもあったのです。
家康の人質時代に培われた「本心を見せない」という処世術が、狸のイメージと重なったのは偶然ではないでしょう。
当時の「狸」は褒め言葉でもあった
現代では「狸」と呼ばれると悪口に聞こえますが、戦国時代の感覚は少し違います。狡猾さは生き残るための必須能力だったからです。
裏切りや暗殺が日常茶飯事だった時代、単純で正直な武将は長生きできませんでした。策略を巡らせる能力は、優れた指導者の証でもあったわけです。
家康が「狸」と呼ばれたことは、敵からも一目置かれていた証拠といえます。畏怖と尊敬が入り混じった、複雑なあだ名でした。
現代での「狸」の意味とは?

現代における「狸」とは、単なる動物の名前を超えた特別な意味があります。日本文化において、狸は象徴的な意味のある動物なのです。
昔のイメージ
日本の昔話では、狸はよく人を化かす動物として登場します。「かちかち山」や「ぶんぶく茶釜」など、狸が変幻自在に姿を変える物語は多いです。
民話の影響で、狸は「見た目は愛らしいが、実は人を騙す狡猾な存在」というイメージが定着しました。無害に見えても、実際は計算高く行動する人を「狸」と呼ぶ文化も生まれてます。
家康の場合も、温厚な外見の裏に、非常に巧妙な政治戦略を隠していました。敵対勢力から見れば、まさに「狸に化かされている」ような感覚だったに違いありません。
今のイメージ
現代でも「あの人は狸だ」という表現は、政治家や経営者を評する際によく使われます。必ずしも悪口ではなく、その人の巧妙さや戦略性を認めつつも、警戒心を示す言葉です。
方広寺鐘銘事件は、家康の狡猾さがわかります。豊臣秀頼が再建した方広寺の鐘に刻まれた「国家安康」「君臣豊楽」という文字に対し、家康は「家康の名を分断し、豊臣を君として楽しむという呪いが隠されている」と言いがかりをつけました。
しかし、方広寺の鐘は現在も京都に残っていて、普通の銘文であることがわかっています。つまり、家康は豊臣家を攻撃する口実が欲しかっただけで、呪いなど全くの作り話だったのです。
他の武将からの徳川家康の呼ばれ方
徳川家康は「狸親父」以外にも、同時代の武将たちからさまざまな呼び方をされていました。織田信長や豊臣秀吉との関係性によって、呼び名も変化していったのです。
織田信長からの呼ばれ方
織田信長は家康のことを「三河殿」と呼んでいました。家康の領地である三河国(現在の愛知県東部)にちなんだ呼び方です。
信長と家康は、清洲同盟を結んだ対等な同盟者でした。しかし実際の力関係では、信長が圧倒的に上だったことは明らかです。
信長の記録には「家康は律儀者」という評価も残っています。約束を守り、裏切らない誠実さを信長は高く評価していたようです。
本能寺の変の直前、家康は信長に招かれて安土城を訪問していました。信長は家康を丁重にもてなしており、信頼関係の深さがうかがえます。
豊臣秀吉からの呼ばれ方
豊臣秀吉は家康のことを「内府殿」と呼ぶことが多かったようです。内府とは内大臣の別称で、家康の官位にもとづいた敬称です。
秀吉と家康の関係は、同盟者でありながらライバルという複雑なものでした。小牧・長久手の戦いでは直接対決し、家康が勝利をおさめています。
秀吉は家康の実力を認めつつも、常に警戒心を持っていました。「家康を敵に回すな」という遺言を残したとも伝えられています。
秀吉が「猿」と呼ばれていたことを考えると、「狸」と「猿」の対比は当時から意識されていたことがわかります。
武田信玄からの称号
家康には「海道一の弓取り」という有名な称号もあります。弓取りとは武将を意味し、東海道で最も優れた武将という意味です。
この称号は武田信玄から贈られたとされています。信玄は家康の軍事的才能を高く評価していたようです。
三方ヶ原の戦いでは家康は信玄に大敗しましたが、それでも「海道一の弓取り」の評価は揺らぎませんでした。敗北から学び、成長し続ける姿勢が認められたのです。
徳川家康の幼名の変遷
徳川家康は生涯で何度も名前を変えています。幼名の「竹千代」から「家康」に至るまで、名前の変化は家康の人生の転機を映し出しているのです。
「竹千代」時代
家康は1542年、三河国岡崎城で生まれました。幼名は「竹千代」で、松平家の嫡男に代々つけられる名前でした。
竹千代という幼名には「竹のようにすくすく育ってほしい」という願いが込められています。松平家では縁起の良い名前として、大切にされてきました。
しかし、竹千代の幼少期は苦難の連続でした。わずか6歳で今川家への人質となり、故郷を離れることになったのです。
その後、織田家の人質として過ごした時期もあります。竹千代という名前で呼ばれた時代は、家康にとって最も辛い時期だったといえます。
「松平元信」「元康」時代
家康は15歳で元服し、「松平元信」と名乗りました。元信の「元」は今川義元から一字をもらったものです。
人質の身でありながら今川家の重臣の娘を妻に迎え、松平元康と改名します。元康という名前にも義元の「元」が含まれていました。
1560年の桶狭間の戦いで今川義元が討たれると、家康の運命は大きく変わります。今川家から独立し、織田信長と同盟を結ぶ決断をしたのです。
今川家との決別を示すため、家康は「元」の字を捨てて「家康」と改名しました。名前を変えることで、新しい人生を歩む決意を表明したのです。
「徳川家康」時代
1566年、家康は姓を「松平」から「徳川」に変更しました。朝廷から正式に徳川姓を名乗る許可を得たのです。
徳川という姓は、先祖が住んでいたとされる上野国徳川郷に由来します。源氏の血を引く名門であることを示す狙いがありました。
松平から徳川への改姓は、単なる名前の変更ではありません。天下を狙える格式を手に入れるための、戦略的な判断だったのです。
「徳川家康」という名前は、「狸親父」と呼ばれた男が天下統一を果たすまでの長い道のりを象徴しています。名前の変遷をたどることで、家康の成長と野望がより深く理解できるはずです。
徳川家康の他のあだ名一覧
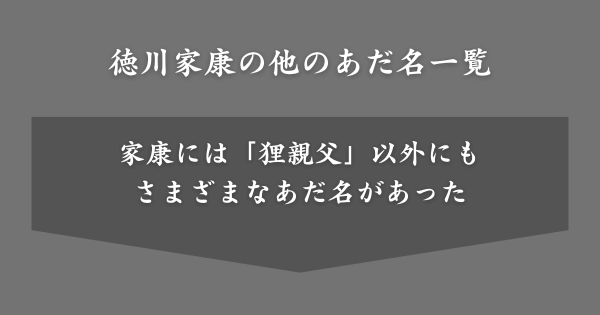
徳川家康には「狸親父」以外にも、さまざまなあだ名があります。それぞれの由来もまとめているため、あだ名から家康の人生も知れるはずです。
| あだ名 | 由来・意味 |
| 東照大権現(とうしょうだいごんげん) | 家康が亡くなった後、神様として祀られた時の名前です。「東照」は「日本の東の方を照らす」という意味で、「大権現」は仏様が神様の姿になって現れることを表しています。日光東照宮という立派なお宮で今でも祀られています。 |
| 神君(しんくん) | 家康を神様のような偉大な君主として敬って呼ぶ時の名前です。江戸時代の人々が家康を非常に尊敬していたことがよくわかる呼び方ですね。 |
| 権現様(ごんげんさま) | 東照大権現を短くして、親しみを込めて呼んだ名前です。江戸時代の庶民が家康を身近な存在として慕っていたことを表しています。 |
| 竹千代(たけちよ) | 家康の幼名(子供の頃の名前)です。今川家や織田家で人質として過ごしていた頃に使われていた名前で、苦労の多い少年時代を表しています。 |
| 三河殿(みかわどの) | 家康が三河国(現在の愛知県東部)の大名だった頃の呼び名です。家康の出身地であり、最初の領地でもある三河への愛着を示しています。 |
| 内府(だいふ) | 家康が朝廷から「内大臣」という高い位をもらった時の呼び名です。とても偉い役職についたことを表す格式の高い呼び方でした。 |
| 大御所(おおごしょ) | 将軍の位を息子に譲った後の家康を指す呼び名です。表向きは引退しているけれど、実際は政治の実権を握っている状態を表しています。 |
徳川家の他のあだ名一覧
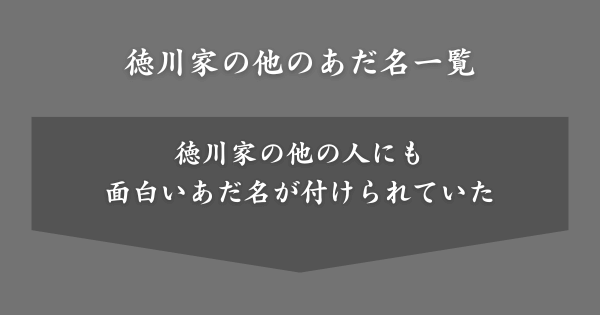
家康だけでなく、徳川家の他の人にも面白いあだ名が付けられていました。それぞれの人物の特徴や時代背景を反映しているため、歴史の勉強にもなるはずです。
| あだ名 | 由来・意味 |
| 暴れん坊将軍(あばれんぼうしょうぐん)※8代将軍吉宗 | 徳川吉宗のことで、テレビドラマで有名になった呼び名です。実際は政治改革に熱心で、庶民のために働く将軍として親しまれていました。「暴れん坊」は正義のために積極的に行動することを表しています。 |
| 犬公方(いぬくぼう)※5代将軍綱吉 | 徳川綱吉のことで、犬を大切にする法律「生類憐みの令」を作ったことから付けられました。動物を大事にしすぎて、時には人間よりも犬を優先したため、皮肉を込めて呼ばれるようになりました。 |
| 鎖国の将軍(さこくのしょうぐん)※3代将軍家光 | 徳川家光のことで、日本を外国から閉ざす「鎖国政策」を完成させたことから付けられました。外国との交流を制限して、日本独自の文化を守ろうとした政策を表しています。 |
| 大樹公(たいじゅこう)※歴代将軍の敬称 | 徳川将軍家全体を指す尊敬の呼び名です。「大樹」は大きくて立派な木のことで、徳川家が日本を支える大きな存在であることを表現しています。 |
| 葵の御紋(あおいのごもん)※徳川家の家紋 | 徳川家の家紋である三つ葉葵を指す呼び名です。この紋章を見ただけで徳川家の権威がわかるほど、江戸時代には恐れられ、尊敬されていました。 |
| 征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)※将軍の正式名称 | 徳川家の当主が代々受け継いだ日本の最高権力者としての正式な役職名です。「征夷」は昔、朝廷に従わない人々を討伐することを意味していましたが、江戸時代には日本全体を治める意味になりました。 |
| 尾張殿・紀伊殿・水戸殿(おわりどの・きいどの・みとどの)※御三家 | 徳川家康の息子たちが治めた尾張・紀伊・水戸の三つの藩を指す呼び名です。将軍家に跡継ぎがいない時は、この三家から新しい将軍を選ぶという大切な役割がありました。 |
【まとめ】徳川家康のあだ名
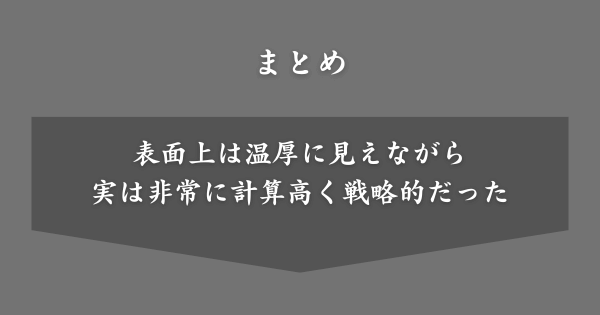
徳川家康の「狸親父」というあだ名には、外見以上の深い意味が込められています。表面上は温厚に見えながら、実は非常に計算高く戦略的だった家康の人物像が表れているわけです。
また、家康から始まる徳川一族の様々なあだ名を見ると、それぞれの時代背景や個性がよく理解できます。
「犬公方」と呼ばれた綱吉の動物愛護政策や、「暴れん坊将軍」で有名な吉宗の改革精神など、あだ名は歴史を身近に感じさせてくれるものでもあります。
さまざまな呼び名を通じて、徳川家の人がより身近な存在として感じられますね。








