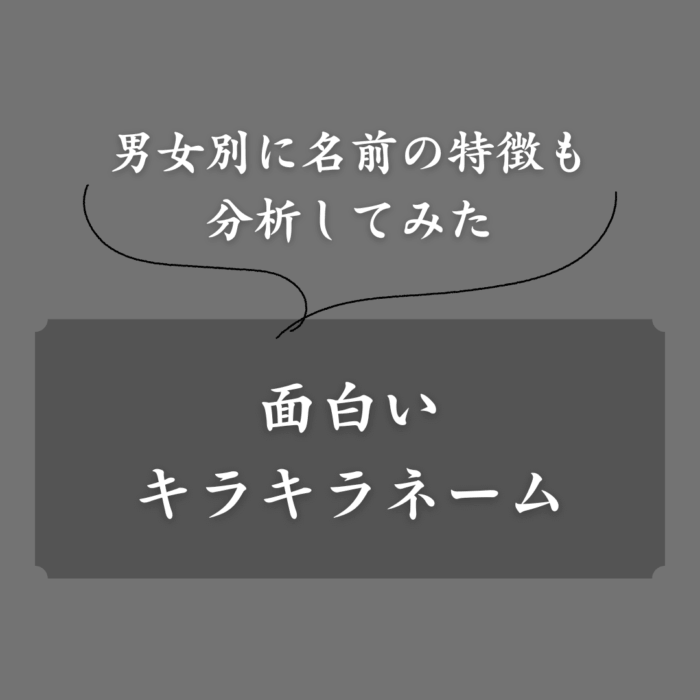キラキラネームが事実上、規制される時代が始まりました。
これから子どもの名前を考える方、すでにキラキラネームの方にとって、重要な情報をまとめました。新しい命名ルールを正しく理解し、適切な判断ができるよう詳しく解説します。
- キラキラネームを規制する法律とは?
- 規制対象になるキラキラネームの条件
- 出生届が受理された・されなかった例
- キラキラネームが規制された元の事件
- 今後キラキラネームをつけられない?
- 既存のキラキラネームはどうなる?
- 改名が受理されなかった場合の対処法
キラキラネームを規制する改正戸籍法とは?

改正戸籍法は戸籍制度創設以来の大きな変革であり、キラキラネーム規制の法的根拠となる法律です。
これまで戸籍には漢字の氏名のみが記載されていましたが、今後は読み方も併記されるようになりました。改正戸籍法により、名前の読み方に初めて法的な基準が設けられたのです。
改正戸籍法の施行スケジュール
2024年5月26日の施行日以降、全国の市区町村から戸籍に登録されている人宛てに、読み方の届出に関する通知書が順次送付されています。
通知書には住民基本台帳や各種証明書から推定された氏名の読み方が記載されており、内容に誤りがある場合は修正手続きをしないといけません。
通知書の修正期限は、2026年5月26日までの2年間です。修正の届出方法は「市区町村の窓口への直接提出」「マイナポータルでのオンライン申請」「郵送による提出」の3つがあります。
期限内に修正の届出をしなくても、ペナルティは課されません。ただし、市区町村長が住民基本台帳や各種証明書の情報から読み方を記載するため、間違った読み方で登録される可能性があります。
もし誤った読み方で登録された場合でも、1度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更が認められる救済措置も設けられています。
改正戸籍法の目的
改正戸籍法の目的は、「行政手続きの円滑化」「本人確認の利便性向上」「金融機関等での本人確認の潜脱防止」の3点です。
特に、金融口座の開設時に読み方を変えることで別人を装う「不正行為への防止効果」が期待されています。
マイナンバーカードの普及と連動したデジタル構築も、改正戸籍法が必要な背景です。
行政手続きのDX化により、各種申請や届出における氏名照合の精度が向上しました。そのため、転居届や各種証明書の発行、社会保険の手続きなどがよりスムーズになりました。
しかし現段階では、国民の利便性よりも行政の管理効率を優先した側面が強いという指摘もあります。戸籍制度のデジタル化は必要ですが、国民目線での運用改善が今後の重要な課題です。
出生届に適用される命名基準
改正戸籍法は、新生児の出生届に適用される新しい命名基準でもあります。法務省は戸籍法に「氏名として用いる文字の読み方は、一般に認められているものでなければならない」という条項を新設しました。
つまり、今後は漢字の意味や読み方と関連性のないフリガナは、原則として認められなくなるということです。
新しい基準が定められた背景には、戸籍実務の現場で氏名と関連性のないフリガナが届出された際の対応が難しい実情があります。
法務省によると「氏名と関連性のないフリガナが届け出られた際の対応を考えると、氏名とまったく関連性のない読み方は認められない旨の規定を設ける必要がある」とされたことが、法改正のきっかけだったようです。
出生届の受理判断は、従来通り各市区町村が行います。法務省はガイドラインを提供しますが、最終的な判断は地方自治体の担当者に委ねられています。
規制対象になるキラキラネームの条件
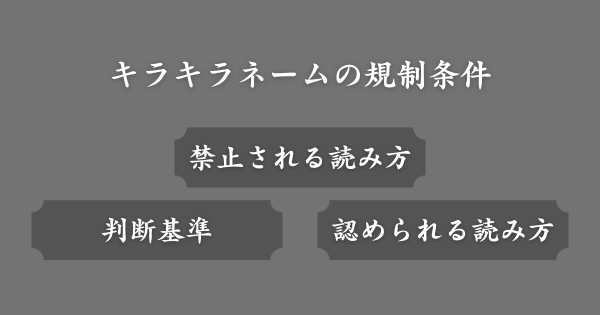
法務省が発表したガイドラインでは、認められないフリガナと認められるフリガナが具体例とともに示されています。今後命名する際に大きな影響を与えるため、詳しく理解しておきましょう。
禁止される4つの読み方パターン
1つ目の禁止パターンは、漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方です。
例として、「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる場合が挙げられます。漢字本来の意味や音訓読みと全く関係のない外国語を当てはめた例で、一般的に認められていません。
2つ目の禁止パターンは、漢字に対して明らかに異なる別の単語を付けた読み方です。
例として、「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませるケースが該当します。漢字1文字に対して、複数の音を無理やり追加する読み方は、一般的に認められていません。
3つ目の禁止パターンは、漢字の持つ意味とは反対の意味で読ませたり、誤解するように読ませたり、混乱させる読み方です。
例として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませるケースです。意図的に混乱を招く可能性のある読み方として、問題視されています。
4つ目の禁止パターンは、差別的・卑わい・反社会的な読み方です。社会通念上相当とはいえないとして、明確に禁止されています。
例は公表されていませんが、社会の健全性と秩序を保つための重要な措置として、位置づけられています。
認められる読み方の判断基準
法務省は「社会において受容され、慣用されているかという観点から判断される」という基準を示しています。単に辞書に載っているかどうかではなく、実際の社会での使用状況を重視する意味です。
たとえば、「美空(そら)」や「彩夢(ゆめ)」などの置き字を用いた読み方は、近年広く使用されていて、社会において受容されていると考えられています。
一方で、「健(ケンサマ)」のような読み方は、社会において受容され慣用されているとはいえません。社会を混乱させるものと判断されてしまいます。
基準においては、時代の変化とともに社会の受容度も変わることが想定されます。現在は新しく感じられる読み方も、将来的には一般的になる可能性があり、柔軟な運用が必要不可欠です。
認められる3つの読み方パターン
1つ目の認められるパターンは、漢字の一部を当てる読み方です。「心愛」を「ココア」、「桜良」を「サラ」と読ませる例があります。漢字の音を部分的に使用した表現として、許容されています。
2つ目の認められるパターンは、熟語としての一般的な読み方です。「飛鳥」を「アスカ」、「五月」を「サツキ」と読ませるのが該当します。日本語の伝統的な読み方で、辞書にも掲載されている表現です。
3つ目の認められる読み方は、置き字を含む読み方です。「美空」を「ソラ」、「彩夢」を「ユメ」と読ませる例で、一部の漢字を読まない表現です。
置き字という技法は、1300年の歴史を持つ日本語の伝統的な表現手法になります。「大和(やまと)」の「大」は中国風に見せるために添えられた文字で、実際には読まれません。
現代のキラキラネームの中にも、置き字を使用したものが多くあります。
出生届が受理されたキラキラネームの具体例
キラキラネームの多くは、実際に出生届として受理されています。以下の表では、実際に戸籍登録されたキラキラネーム例をまとめました。
| 名前 | 読み方 | 受理された理由 |
| 光宙 | ぴかちゅう | 「光」が「ぴか」、「宙」が「ちゅう」と読めるため、漢字の音を部分的に使った名前として認められました。 |
| 心愛 | ここあ | 「心」を「ここ」、「愛」を「あ」と読ませる形式で、漢字の一部を使用した読み方として受理されています。 |
| 飛鳥 | あすか | 奈良時代から使われている地名に由来する読み方で、辞書にも載っている伝統的な名前として受理されています。 |
| 大翔 | ひろと | 「大」を「ひろ」、「翔」を「と」と読ませる形式で、漢字の訓読みの一部を使った名前として認められました。 |
| 海月 | みづき | 「海」を「み」、「月」を「づき」と読ませる形式で、自然をイメージした美しい名前として認められました。 |
| 黄熊 | ぷう | ディズニーキャラクターの「くまのプーさん」に由来し、黄色い熊という意味との関連性で受理されました。 |
| 泡姫 | ありえる | ディズニー映画「リトルマーメイド」の主人公に由来し、泡と姫という漢字の意味との関連性で認められました。 |
| 皇帝 | しいざあ | ローマ皇帝の称号「シーザー」に由来し、漢字の意味と読み方に関連性があるとして受理されています。 |
| 騎士 | ないと | 「騎士」は英語で「knight」という意味で、漢字の意味と読み方が対応しているため認められました。 |
| 七音 | どれみ | 音楽の「ドレミ」と7つの音を表す漢字との関連性があり、意味がつながる名前として認められました。 |
| 今鹿 | なうしか | 映画「風の谷のナウシカ」に由来し、「今」を「なう」と読ませる現代的な表現として受理されました。 |
| 姫星 | きてぃ | キャラクター「ハローキティ」に由来し、「姫」と「星」の漢字からイメージできる読み方として認められました。 |
| 美俺 | びおれ | 化粧品ブランド名に由来しますが、「美」と「俺」の読みを組み合わせた名前として受理されています。 |
| 陽葵 | ひまり | 「陽」を「ひま」、「葵」を「り」と読ませる形式で、太陽と花を組み合わせた人気の名前として受理されています。 |
| 結愛 | ゆあ | 「結」を「ゆ」、「愛」を「あ」と読ませる形式で、近年とても人気が高い名前として受理されています。 |
出生届が受理されなかったキラキラネームの具体例
極端なキラキラネームは、出生届を受理されないケースがあります。以下の表では、受理されなかったキラキラネーム例と理由をまとめました。
| 名前 | 読み方 | 受理されなかった理由 |
| 悪魔 | あくま | 1993年の有名な事件で、子どもがいじめられる可能性が高く、子どもの幸せに反すると判断されました。 |
| 高 | ひくし | 「高い」という意味の漢字に「低い」を連想させる読み方を当てることは、混乱を招くため認められませんでした。 |
| 太郎 | じろう | 「太郎」という名前に別の名前「次郎」を当てる読み方は、わざと間違いを起こすものとして受理されません。 |
| 健 | けんいちろう | 漢字1文字「健」に対して「けんいちろう」という長い読み方を当てることは、認められていません。 |
| 美 | びじょ | 漢字1文字「美」に対して「美女」という別の単語を当てはめることは、認められないパターンです。 |
| 幸 | ふこう | 「幸せ」という意味の漢字に「不幸」という正反対の読み方を当てることは、子どもの幸せに反します。 |
| 王子 | おれさま | 漢字の意味とは関係のない「俺様」という読み方は、社会で受け入れられている読み方ではありません。 |
| 天才 | じーにあす | 漢字「天才」に英語の「genius」を当てはめる読み方は、社会で広く使われている読み方ではありません。 |
| 姫 | ぷりんせす | 「姫」という漢字に英語の「princess」を当てはめる読み方は、一般的に認められていない読み方です。 |
| 戦士 | うぉーりあー | 「戦士」を英語の「warrior」と読ませることは、日本語の読み方として受け入れられていません。 |
| 救世主 | めしあ | 「救世主」を「メシア」と読ませる場合、宗教的な意味合いが強く、一般的な名前とは認められません。 |
| 魔王 | でびる | 「魔王」という漢字に「デビル」という読み方を当てても、子どもの幸せを考えると認められません。 |
| 死神 | りーぱー | 「死神」という漢字自体が名前としてふさわしくなく、子どもの将来に悪い影響を与える可能性があります。 |
| 暗黒 | だーくねす | 「暗黒」という否定的な意味の漢字は名前として不適切で、子どもの幸せに反すると判断されました。 |
キラキラネームが規制されたきっかけの事件
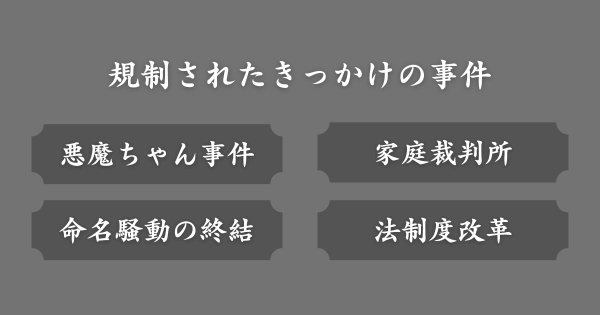
キラキラネーム規制の背景は、1993年に発生した「悪魔ちゃん命名騒動」にあります。現在の規制制度につながる重要な事件で、命名権と社会通念の関係について問題提起しました。
悪魔ちゃん命名騒動とは?
1993年8月11日、東京都昭島市役所に「悪魔」という名前の男児の出生届が提出されました。提出時点では、「悪」も「魔」も戸籍法50条で定められた範囲内であったため、窓口では受理手続きが開始。
しかし、その後戸籍課職員の間で「子の名前として適切か」疑義が生じ、法務省への照会が行われました。
最初の法務省からの回答は、「常用漢字の範囲内であり法的に問題ない」というものでしたが、その後社会的な注目を集める中で、方針が変わります。
数日後、法務省から「子の名を『悪魔』とするのは妥当ではない。子の福祉に反する」という指示が出されました。方針転換の結果、すでに開始されていた受理手続きが中止される事態になったのです。
家庭裁判所での争い
法務省からの判断を受けて、届出者である父親は1993年9月に家庭裁判所に不服申し立てを行いました。
父親側の主張は、「常用漢字の範囲内であり、法的な問題はない。親の命名権を不当に制限するものだ」というもの。
事件は連日マスコミで報道され、「悪魔ちゃん命名騒動」として社会的な議論を巻き起こしました。賛成派は「親の権利を尊重すべき」、反対派は「子どもの将来を考えるべき」という主張を展開します。
法廷では、「命名権の範囲」「子の福祉」「社会通念の定義」などについて議論が交わされました。裁判の過程で、これまで明確でなかった命名に関する法的基準の曖昧さが浮き彫りになったのです。
悪魔ちゃん命名騒動の終結
1994年2月14日、父親が不服申し立てを取り下げたことで、法的な争いは終了しました。
その後、父親は「阿久魔」という当て字での命名を提案しましたが、法務局から「読み方が『あくま』である限り、当て字でも認められない」と返答。
最終的に、父親は1994年5月に別の名前で出生届を提出し、一連の騒動は終結しました。しかし、悪魔ちゃん事件が日本に与えた影響は、非常に大きかったです。
当時の法務大臣は、国会答弁で「社会通念に照らして親の命名権の濫用にあたる」との見解を示し、法務省の判断を正当化しました。
同時に、「命名の基準のような価値評価がからむ事案に、行政庁が一律の基準を作るのは難しい」とも述べています。今回の法改正における課題を予見していたといえます。
法制度改革への影響
悪魔ちゃん事件から学べる教訓は、常用漢字の範囲内であっても、社会通念に反する名前は認められないことが明確になりました。
また、行政の判断が必ずしも一貫していないことも浮き彫りになり、明確な基準の必要性が認識されました。
重要な点は、親の命名権が無制限ではないことです。子どもの福祉や社会秩序とのバランスが求められることが議論されました。
悪魔ちゃん事件により、命名権と社会秩序のバランスをどこに置くかという問題が、現在でも解決されていない根本的な課題として残っています。
事件後、法務省では命名に関する内部基準の整備が進められ、各自治体への指導も強化されました。今回の改正戸籍法による明文化は、30年間の議論の集大成といえます。
今後はキラキラネームをつけられない?

改正戸籍法の施行により、極端なキラキラネームは確実に制限されます。ただし、完全な禁止ではなく、日本語の表現方法に基づいた個性的な名前は、引き続き認められる見込みです。
出生届の新しい審査プロセス
新生児の出生届の審査は、引き続き各市区町村の窓口で行われます。
ただし、法務省のガイドラインに基づいた判断基準が適用されるようになりました。審査担当者は事前に研修を受け、一定の知識を身につけた上で判断を行うことになっています。
出生届が受理されそうにない場合、救済措置として、漢字の由来や読み方の意味を説明する書類の提出が認められています。「日本の命名文化を踏まえて運用する」という国会での付帯決議に基づくものです。
具体的には、古典文学からの引用、地名や人名での使用例、言語学的な説明などを資料として提出できます。前例のない名前については、読み方の由来を説明することで受理されるかもしれません。
判断格差解消への取り組み
自治体間での判断基準の違いについては、法務省による対策が講じられています。
2007年の「稀星(きらら)事件」では、立山町で受理されなかった名前が隣の富山市では受理されるという事態が発生しました。
そこで、法務省では全国の市区町村担当者向けの研修プログラムを充実させました。「ガイドラインの詳細な説明」「判断に迷うケースの事例」「専門家による講義」などが含まれています。
判断に迷うケースについては、法務局への相談制度も整備されています。各自治体の担当者が判断に困った場合は、法務局の専門官に相談し、見解を得ることができる仕組みです。
一部の自治体では、出生届提出前の命名相談窓口を設置する動きも見られます。事前に名前の読み方が受理されるかどうかを相談できるサービスです。
法務省も公式Webサイトにて、認められる読み方と認められない読み方の例を公開しています。出生届提出時のトラブルを未然に防ぐ効果が期待されます。
既存のキラキラネームはどうなる?

すでに戸籍に登録されているキラキラネームは、基本的に変更を求められることはありません。ただし、フリガナの登録過程で一部影響を受ける可能性はあります。
現在の名前に対する措置
既存の名前については、住民基本台帳や各種証明書などの情報をもとに市区町村がフリガナを推定して登録します。可能な限り本人や家族が実際に使用している読み方を尊重する方針が取られているわけです。
ただ、間違ったフリガナで登録された場合は、1度だけ家庭裁判所の許可なしで変更できます。2回目以降の変更については、家庭裁判所の許可が必要になりますが、最初の1回目は特別な救済措置が設けられているのです。
法務省は「現在使用されている方もいる可能性がある」として、名前の当否について公的な言及を避けています。キラキラネームの人への配慮であり、人権保護の観点から重要な姿勢といえます。
フリガナ登録に関する手続き
フリガナ登録の通知を受け取った方で、記載内容に間違いがある場合の修正手続きは簡単です。「市区町村窓口での直接申請」「マイナポータルでのオンライン申請」「郵送での申請」の3つがあります。
必要な書類は本人確認書類と印鑑程度で、特別な証明書類は必要ありません。家族による代理申請も可能で、高齢者や体が不自由な方への配慮もされています。
家庭裁判所の許可が必要になる場合は除きますが、手数料は無料で何度でも修正できます。国民に新たな負担を課さないという、政府の方針に基づくものです。
将来の命名文化への影響
国語学者の笹原宏之早稲田大学教授は、規制の行き過ぎによる弊害を強く警告しています。
教授によると、「新しい発想の命名を認めなければ、『飛鳥』や『和子』のような名前は一切生まれなくなってしまう」と指摘しています。
日本語の漢字表記は、1300年にわたって自由な発想で新しい名前を生み出してきました。
置き字を利用した「大和(やまと)」や、読み方の由来がわかっていない「飛鳥(あすか)」など、現在当たり前とされている言葉も、当初は革新的な試みだったのです。
北海道から沖縄まで800万人の名前データを調査した結果、キラキラネームと呼ばれる名前の多くが、実は日本語の伝統的な表現方法に基づいていることも判明しています。
核家族化による命名文化の変化
核家族化の進行が命名文化に与える影響も指摘されています。笹原教授は、「極端な名前について、意見を言う上の世代が介在しなくなった」ことを重要な変化として挙げています。
かつては祖父母や親戚が命名に関わることが多く、極端な名前には自然にブレーキがかかっていました。
しかし、現代では若い夫婦だけで名前を決めるケースが増え、結果として社会常識から外れた名前が付けられることもあります。
現在の状況を改善するために、教授は「名づけるときには、名前が社会でどう受け取られるのか、命名権をもつ親にはしっかりと考える義務と責任がある」と強調しました。
日本語や漢字の歴史について学び、社会性を考慮した命名を行うことの重要性を訴えています。
キラキラネームの改名が受理されなかった場合の対処法
キラキラネームの改名を申請しても、家庭裁判所で却下されるケースがあります。しかし、諦める必要はありません。改名が受理されなかった場合の対応策を解説します。
即時抗告を申し立てる
家庭裁判所の却下決定に不服がある場合、「即時抗告」という手続きが可能です。
即時抗告とは、家庭裁判所の決定に対して、上級の高等裁判所に再審査を求める手続きです。却下決定の告知を受けてから2週間以内に申し立てる必要があります。
申立先は、却下決定をした家庭裁判所ではなく、管轄の高等裁判所です。申立書には却下決定に対する不服の理由を具体的に記載しなければなりません。
即時抗告の費用は、収入印紙代として1,800円程度が必要です。弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。自分で手続きを行うことも可能ですが、法的な知識が求められるため、専門家への相談をおすすめします。
却下理由を分析して再申請する
即時抗告ではなく、改めて申請し直す方法もあります。
家庭裁判所が改名を認めるには「正当な事由」が必要です。却下された場合、申請時の理由や証拠が不十分だった可能性があります。却下理由を詳しく分析し、補強した上で再申請してください。
改名が認められやすい「正当な事由」には、以下のようなものがあります。
- 社会生活上の著しい支障がある
- 同姓同名の犯罪者がいる
- 性同一性障害による
キラキラネームの改名では、「社会生活上の著しい支障」を証明する資料が有効です。いじめの被害や精神的苦痛を示す診断書などを準備しましょう。
通称名の使用を検討する
法的な改名が難しい場合、通称名を使用する方法があります。
通称名とは、戸籍上の本名とは別に、日常生活で使用する名前のことです。法律で禁止されているわけではなく、一定の条件下で社会生活に使用できます。
会社や学校では、通称名での呼称を認めてもらえる場合があります。就業規則や校則で、通称名の使用が認められている職場や学校も増えています。まずは上司や担任に相談してみましょう。
通称名を長期間使用し続けることで、将来的に改名が認められやすくなる可能性もあります。社会生活で定着した通称名への変更は、「正当な事由」として認められやすいためです。
弁護士に相談する
改名手続きで困った場合、専門家である弁護士への相談が有効です。
家事事件に詳しい弁護士は、改名が認められるための戦略を立ててくれます。過去の判例や成功事例をもとに、最適な申請方法をアドバイスしてもらえるはずです。
初回相談は無料の法律事務所も多くあります。各地域の弁護士会が運営する法律相談窓口も利用できます。費用面で不安がある場合は、法テラスの無料法律相談を活用するのも1つの方法です。
弁護士費用の相場は、相談料が30分5,000円程度、手続き代理の場合は10万円から30万円程度です。費用対効果を考慮した上で、依頼するかどうかを判断しましょう。
【まとめ】キラキラネームの規制
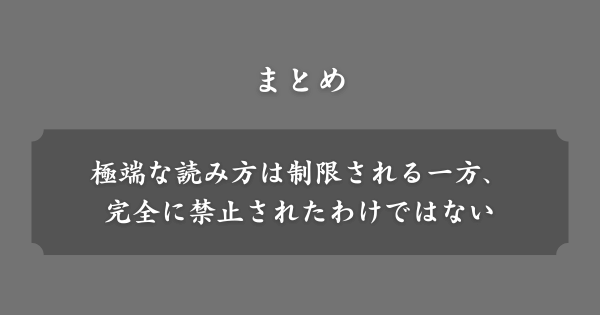
改正戸籍法によるキラキラネーム規制は、日本の命名文化における大きな転換点です。極端な読み方は制限される一方、完全に禁止されたわけではありません。
重要なポイントは、漢字の意味と読み方の関連性です。「美空(ソラ)」のような置き字や「心愛(ココア)」のような部分読みは認められますが、「太郎(マイケル)」といった無関係な読み方は禁止されます。
すでにキラキラネームの方は、変更を求められることはありません。フリガナ登録時も配慮措置が設けられています。一方、これから命名される方は新基準に従う必要があります。
改正戸籍法により、親には名前の社会性をより深く考える責任が求められるようになりました。日本語の表現力を活かしつつ、子どもが誇りを持てる素晴らしい名前を選ぶことが大切です。