妊娠がわかったとき、お腹の赤ちゃんに愛称をつける「胎児ネーム」という文化があります。しかし、一部の人からは「気持ち悪い」という声も聞かれるのが現実です。
今回は、胎児ネームに対する様々な意見や実際の統計、メリットなどについて詳しく見ていきましょう。
- 胎児ネームは気持ち悪い?
- つけている人はどれくらい?
- 胎児ネームのメリットは?
- 胎児ネームをつける時期は?
- 胎児ネームと本名は違う?
胎児ネームをつけるのは気持ち悪い?

「胎児ネームが気持ち悪い」と感じる人は一定数いますが、多くの妊婦さんにとっては自然な愛情表現の一つです。
胎児ネームに対する賛否両論の声を詳しく見ていきましょう。
否定的な意見
胎児ネームに否定的な人たちは、まだ生まれていない赤ちゃんに名前をつけることに違和感を持っていることが、気持ち悪いと思う理由の1つです。
「赤ちゃんがお腹の中にいる段階で名前をつけるのは早すぎる」という意見があります。実際の姿を見る前に愛称をつけることに、抵抗を感じる人も多いのです。
また、SNSで「今日も〇〇ちゃんが元気に動いています」などの投稿に対して、気持ち悪いと感じる人もいます。特に子どもがいない人や妊娠経験のない人には、理解しがたい行為に映ってしまうのです。
「ぷーちゃん」「みーたん」などの可愛すぎる愛称に対して、大人が使う言葉として適切ではないという意見もあります。
肯定的な意見
胎児ネームを支持する声もあり、まず多くの産婦人科医が胎児ネームの使用を推奨しています。お腹の赤ちゃんに話しかけることで、母親としての自覚が芽生えやすくなるためです。
臨床心理士によると、胎児ネームは妊娠への不安を軽減し、母性を育む効果があるとされています。特に初産の妊婦さんにとって、心理的な支えになることが多いです。
また、夫と一緒に胎児ネームを考えることで、父親としての自覚も促進されます。妊娠中から育児への参加意識を高める効果があるわけです。
胎児ネームをつけている人はどれくらい?

妊娠経験のある女性の約6割が胎児ネームをつけているという調査結果があり、年々増加傾向にあります。
胎児ネームの実態について、様々な角度から詳しく調べてみました。
全体的な統計データ
2023年に実施された全国規模の妊娠・出産に関する意識調査(対象:過去5年以内に出産経験のある女性3,000名)では、以下のような結果が明らかになりました。
- 胎児ネームをつけた経験がある:58.7%
2018年の調査と比較すると、約8%増加しており、胎児ネーム文化が徐々に浸透していることがわかります。
年代別の傾向
初産が多い20代は「52.3%」です。妊娠に対する新鮮な驚きから胎児ネームをつける傾向があります。SNS世代でもあるため、胎児ネームの共有も積極的です。
最も胎児ネームをつける率が高い30代前半は「67.8%」です。経済的にも精神的にも安定しており、妊娠を心から楽しむ余裕があることが影響しています。
キャリアを積んだ後の妊娠が多く、計画的に妊娠に臨む人が多い30代後半は「61.2%」です。胎児ネームも慎重に選ぶ傾向があります。
高齢出産への不安もあり、胎児ネームよりも健康面に意識が向きがちな40代以上は「43.7%」です。ただし、待望の妊娠の場合は積極的につける人も多いです。
地域別の傾向
情報量が多く、妊娠関連のトレンドにも敏感な都市部では「64.2%」でした。産婦人科でも胎児ネームについて、積極的に話題にする機会が多いようです。
地方都市では「55.8%」でした。都市部ほどではありませんが、半数以上の妊婦さんが胎児ネームを使用しています。家族や親戚との距離が近く、胎児ネームを共有する機会も多いです。
農村部・山間部では「47.3%」でした。伝統的な価値観を重視する地域では、胎児ネームの使用率がやや低めです。ただし、若い世代では都市部と変わらない傾向も見られます。
初産と経産婦の傾向
初産婦は「69.4%」と、初めての妊娠への特別感から、胎児ネームをつける率が高くなっています。妊娠中の変化を一つひとつ大切にする傾向があります。
経産婦(2人目)は「52.1%」と、1人目の育児経験から、より現実的になる傾向があります。ただし、性別が違う場合は、新鮮さから胎児ネームをつけることが多いです。
経産婦(3人目以降)は「41.8%」と、妊娠や出産に慣れており、胎児ネームをつける率は最も低くなっています。実用的な面を重視する傾向が強いです。
SNS普及の傾向
InstagramやX、妊娠アプリなどの普及により、胎児ネーム文化は大きく変化しました。下記の結果より、SNSで妊娠記録を公開する文化が胎児ネームの普及を後押ししていることがわかります。
- 妊娠アプリ利用者の胎児ネーム使用率:73.2%
- SNS投稿者の胎児ネーム使用率:84.6%
- 妊娠記録を公開している人:91.1%
胎児ネームをつけるメリットは何?

胎児ネームをつけることで得られる効果は様々です。妊娠期間をより充実したものにできる科学的根拠もあります。
胎児ネームがもたらす具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
夫婦の絆が深まる
「〇〇ちゃんはパパに似るかな?」のような会話が日常になることで、夫婦間の絆が深まります。胎児ネームを夫婦で考える過程で、将来の家族像について話し合う機会が自然に生まれるのです。
男性は女性と比べて妊娠を実感しにくいが、旦那は胎児ネームを使うことで父親としての自覚が芽生えやすくなります。
また、つわりや体調の変化など、妊娠中の辛さは男性には理解しにくいものです。しかし、胎児ネームを通じて、妊娠期間を夫婦で一緒に過ごしている実感が得られます。
妊娠を実感できる
妊娠初期は体調不良があっても、赤ちゃんの存在を実感しにくいものです。しかし胎児ネームをつけることで、お腹の中に一つの命があることを意識でき、自然と母性が生まれます。
「赤ちゃんは元気かな?」という不安を抱えがちな妊娠期間中、胎児ネームで話しかけることで、心理的な安定も得られます。名前があることで、より身近で親しみやすい存在として感じられるわけです。
胎児ネームを使って赤ちゃんと対話を続けることで、出産への恐怖よりも「早く会いたい」という期待感が強くなるメリットもあります。
赤ちゃんに良い影響がある
赤ちゃんが音を聞き取れるようになる妊娠20週頃、愛情を込めて胎児ネームで話しかけることで、赤ちゃんの聴覚発達にとって良い刺激になります。
胎児ネームを使って赤ちゃんに話しかけることで、母親のストレスが軽減されると同時に、赤ちゃんにも良い影響があります。母親のストレスホルモンは、胎盤を通して赤ちゃんにも伝わるためです。
胎児ネーム時代から聞いていた声や音楽に、生まれてから特別な反応を示す赤ちゃんもいます。胎内記憶の一種です。
精神的に安定する
体調不良や制限の多い妊娠期間も、胎児ネームがあることで、日々の変化を楽しめるようになります。「今日は〇〇ちゃんがよく動くね」など、小さな発見が喜びになるのです。
家族や友人に胎児ネームを伝えることで、妊娠に対する周囲の理解と協力が得やすくなります。「〇〇ちゃんは元気?」と気にかけてもらえることが、母親にとって心の支えです。
妊娠日記やSNSに胎児ネームで記録することで、妊娠期間の思い出が温かいものになります。後で振り返ったときに、特別な時間として記憶に残っているはずです。
胎児ネームをつける時期はいつ?

胎児ネームをつける時期に決まりはありませんが、妊娠8週から16週頃につける人が多いです。妊娠の各時期における胎児ネームの傾向を詳しく解説します。
妊娠4週〜7週:妊娠判明直後
胎児ネームをつける人の割合は約15%。
妊娠検査薬で陽性が出た直後から胎児ネームをつける人は少数派です。まだ体調の変化も少なく、妊娠の実感が湧かないことが多いためです。
ただし、待望の妊娠だった場合や、2人目以降の妊娠では早い段階からつける人もいます。
妊娠8週〜11週:つわりピーク
胎児ネームをつける人の割合は約35%。
妊娠8週頃に初回の産婦人科受診を行い、心拍が確認されることで妊娠が確定します。つわりによる体調の変化で妊娠を実感することから、胎児ネームをつける人が急増します。
母子手帳の交付を受けるタイミングでもあり、「公式に妊娠が認められた」という気持ちから胎児ネームをつけ始める人も多いです。
妊娠12週〜15週:安定期入り
胎児ネームをつける人の割合は約28%。
安定期に入ることで流産のリスクが大幅に低下し、妊娠を周りに報告し始める時期です。つわりも軽減され、妊娠を前向きに捉えられるようになることから、胎児ネームをつける人も多くなります。
お腹も少しずつ目立ち始め、妊婦さんらしい体型になってくることも胎児ネームをつける理由の一つです。
妊娠16週〜19週:胎動開始
胎児ネームをつける人の割合は約15%。
初産婦は妊娠18週〜20週頃、経産婦は妊娠16週〜18週頃に初回胎動を感じます。お腹の中で赤ちゃんが動いているという実感から、胎児ネームをつける人もいました。
エコー写真でも赤ちゃんの姿がより鮮明に見えるようになり、「手を振っているみたい」「あくびをしている」などの様子から、愛称を思いつくこともあります。
妊娠20週〜23週:性別判明ピーク
胎児ネームをつける人の割合は約12%。
妊娠20週前後で赤ちゃんの性別がわかることが多く、それまで性別に関係ない胎児ネームだった人も、より具体的な名前に変更することがあります。
たとえば、「まめちゃん」だった赤ちゃんが男の子とわかって「まー君」になったり、女の子とわかって「まなちゃん」になったりするケースです。
妊娠24週〜27週:胎動活発化
胎児ネームをつける人の割合は約8%。
胎動がより活発になり、赤ちゃんの個性を感じられるようになる時期です。よく動く赤ちゃんには「げんき」、おとなしい赤ちゃんには「おと」など、胎動の特徴から胎児ネームをつけることもあります。
妊娠28週〜35週:出産準備期
胎児ネームをつける人の割合は約6%。
お腹が大きくなり、出産への実感が高まる時期です。出産準備期に初めて胎児ネームをつける人は少数派ですが、「もうすぐ会える」という気持ちから愛称で呼び始める人もいます。
妊娠36週以降:正産期
胎児ネームをつける人の割合は約3%。
正産期に入ると「いつ生まれても大丈夫」という安心感から、それまで距離を置いていた人も胎児ネームをつけることがあります。
特に高齢出産の場合は慎重になりがちですが、正産期に入ると安心して愛着を表現できるようになります。
胎児ネームは生まれた後の名前とは違う?

胎児ネームと実際の名前は基本的に別物です。約9割の家庭では異なる名前をつけていて、それぞれに明確な役割があります。
胎児ネームと本名の関係について、様々な角度から詳しく見ていきましょう。
胎児ネームと本名の違い
胎児ネームは妊娠期間中のコミュニケーションツールとしての役割が中心で、以下のような特徴があります。
- 親しみやすさ重視
- 漢字や意味よりも呼びやすさを重視
- 愛らしい響きで愛情を表現
- 性別がわからなくても使える名前
- 妊娠期間限定での使用が前提
一方、実際につける名前は一生使うものとして、より慎重に考えられています。
- 将来の職業生活も見据えた名前
- 込めたい願いや意味を重視
- 苗字とのバランスを考慮
- 見た目の美しさや縁起を重視
- 生涯使用することを前提に選択
統計データの結果
過去3年以内の出産経験者2,500名を対象にした、2023年の全国調査結果は下記の通りです。結果からもわかるように、多数の家庭では胎児ネームと本名は別物として考えられています。
- 胎児ネームと本名が全く異なる:87.3%
- 胎児ネームと本名が部分的に関連:8.2%
- 胎児ネームがそのまま本名になった:4.5%
専門家の見解
産婦人科医によると、「胎児ネームと本名は全く別物として考えるのが健全。胎児ネームは妊娠期間を楽しむためのものであり、本名は子供の将来を考えて慎重につけるべき」とされています。
臨床心理士によると、「胎児ネームから本名への移行は、親が子どもを一人の独立した人格として認識する大切なプロセス。全く違う名前をつけることで、子供への期待や愛情が整理される効果もある」とのことです。
命名研究家によると、「近年、胎児ネームと本名の境界が曖昧になる傾向があるが、それぞれの役割を明確にすることで、より良い命名ができる。胎児ネームは『今』を楽しむもの、本名は『未来』を願うものと考えると良い」とされています。
【まとめ】気持ち悪いと言われる胎児ネーム
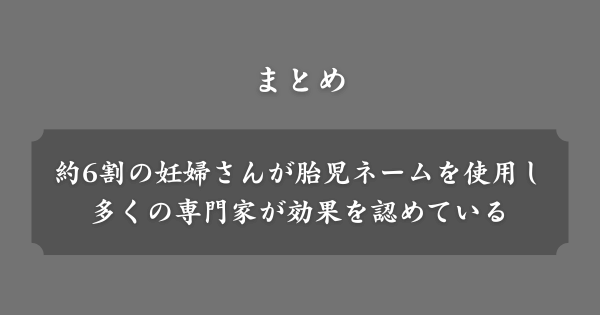
胎児ネームについては、「気持ち悪い」と感じる人もいれば、「素晴らしい」と捉える人もいます。大切なのは、それぞれの価値観や考え方を尊重し合うことです。
統計データからもわかるように、約6割の妊婦さんが胎児ネームを使用していて、多くの専門家がその効果を認めています。夫婦の絆を深め、妊娠期間をより充実したものにする効果があることは確かです。
一方で、胎児ネームをつけないからといって愛情が少ないわけではありません。妊娠への向き合い方は人それぞれであり、どれも正しいです。
胎児ネームを考えている妊婦さんは、自分たちが心地よく感じる方法を選択してください。
妊娠は人生で数回しか経験できない貴重な期間です。周りの意見に惑わされることなく、お腹の赤ちゃんとの特別な時間を大切に過ごしていただければと思います。






