杉田玄白には「やぶ医者だった」という噂や、「草葉の陰」というあだ名の真相まで、知られざるエピソードが盛りだくさんです。
今回は、杉田玄白の人物像を名前の視点からひも解いていきます。
- 「杉田玄白」はあだ名?
- 杉田玄白の意味は「やぶ医者」?
- 杉田玄白のあだ名は「草葉の陰」?
- 杉田玄白の本名・字・号とは?
- 杉田玄白の別のあだ名一覧
「杉田玄白」はあだ名?

杉田玄白はあだ名ではなく、江戸時代の蘭学者として活躍した医師の名前です。
江戸時代の名前について
江戸時代の武士階級では、一人で複数の名前を持つのが一般的でした。具体的には、幼名、諱(いみな)、通称、字(あざな)、号などを使い分けていました。
現代のように、一つの名前で一生を過ごすのとは違い、場面や年齢、地位に応じて名前を変えていたのです。中国文化に影響を受けた日本独特の習慣と言われています。
「玄白」は「字」に相当する名前で、医師として活動する際に使用していました。当時の医師たちは、患者や同業者との関係では、本名(諱)よりも字を使用することが多かったのです。
「杉田玄白」が有名になった理由
「杉田玄白」という名前が有名になった最大の理由は、解体新書の翻訳者としての功績にあります。歴史的な医学書である解体新書は、「杉田玄白」の名前で署名されており、後世に大きな影響を与えました。
また、自伝である蘭学事始も玄白の名前で執筆されています。重要な著作物が「玄白」名義で残されたため、現代でも「杉田玄白」という名前で親しまれているのです。
歴史の教科書でも「杉田玄白」として紹介されるのは、最も活動的だった時期に使用していた名前だからです。
杉田玄白の意味は「やぶ医者」?その理由とは?

杉田玄白の「玄白」という名前が「やぶ医者」を意味するという説は、完全な誤解です。しかし、誤解が生まれてしまった背景には、いくつかの理由があります。
「玄白」の本来の意味
「玄白」の「玄」は、奥深い学問や知識を表す漢字です。老子の思想にも登場する重要な概念で、「玄妙」「玄学」といった言葉にも使われています。
一方、「白」は純粋さや清らかさ、誠実さを象徴しています。
つまり、「玄白」は「奥深い学問を持ちながらも純粋で誠実な人」という、非常に高尚な意味を持つ名前なのです。医師にとって理想的な素晴らしい名前と言えます。
誤解が生まれた理由
「玄白=やぶ医者」という全く逆の解釈が生まれた最大の理由は、当時の医学界における立場の違いにあります。
江戸時代の医学は漢方医学が主流で、中国から伝来した医学理論に基づいて、診断や治療を行うのが常識でした。そんな中、杉田玄白はオランダから伝わった西洋医学に注目しました。
漢方医学の権威者たちからすれば、杉田玄白の取り組みは異端。「長年続いてきた伝統的な医学を否定するのか」「外国の怪しげな学問に惑わされている」などの批判が相次いだのです。
特に「解体新書」の翻訳作業では、人体解剖という当時としては画期的すぎる内容が含まれていました。儒教では「身体髪膚、これを父母に受く」として、死体を解剖することは不道徳とされていたためです。
さらに、オランダ語から日本語への翻訳は想像を絶する困難を伴いました。当時、オランダ語を理解できる日本人は極めて少なく、辞書もほぼありませんでした。
杉田玄白自身も「一日でわずか数行しか進まない」「推測で翻訳せざるを得ない部分が多い」など、蘭学事始で翻訳の苦労を記しています。
困難な状況で翻訳したこともあり、完璧とは言えない部分もありました。そのため、「いい加減な翻訳をしている」「理解できていないのに訳している」など、一部の医師や学者からは厳しい批判を受けることもあったのです。
現代での「玄白」の評価
現代の医学史研究では、杉田玄白の功績は非常に高く評価されています。不利な状況の中でも、西洋医学の導入に挑戦し、日本の近代医学発展の基礎を築いたのです。
「やぶ医者」どころか、日本医学史上最も重要な人物の一人として位置づけられています。時代を先取りした先見性と、困難に立ち向かう勇気を持った偉大な医師だったのです。
杉田玄白のあだ名は「草葉の陰」?その理由とは?

杉田玄白のあだ名として「草葉の陰」が使われたという話については、史料による確実な裏付けがありません。そのため、後世に作られた創作である可能性が高いです。
「草葉の陰」の一般的な意味
「草葉の陰」という言葉は、通常「故人が天国から見守っている」という意味で使用されます。亡くなった人への敬意を込めて、「草葉の陰で喜んでいると思う」のように用いられるのが普通です。
生きている人に対しては、「草葉の陰」を使うことはほとんどありません。そのため、杉田玄白が生前に「草葉の陰」と呼ばれていたという話は、不自然です。
真実だった場合の理由
もし「草葉の陰」が実際に使われていたとすれば、いくつかの理由が考えられます。
まず、杉田玄白の謙虚な人柄が挙げられます。「蘭学事始」を読むと、自分の功績を誇ることなく、むしろ苦労や失敗を正直に記述しています。
「自分などは取るに足らない存在」という謙遜の気持ちから、「草葉の陰」という言葉を使った可能性があります。
また、当時は少数派である西洋医学支持者の杉田玄白は、異端視されることが多々ありました。
正面から西洋医学を主張するよりも、静かに研究を続ける「陰の存在」として活動していたため、「草葉の陰」という表現が生まれた可能性も考えられます。
デタラメだった場合の理由
「草葉の陰」は後から作られた創作だという説のほうが有力です。
明治時代以降、杉田玄白の功績が広く知られるようになると、様々な逸話や伝説が作られました。「草葉の陰」というあだ名も、その過程で生まれた可能性が高いです。
実際の史料に基づかない情報も多く広まっています。そのため、歴史上の人物について語る際は、確実な史料に基づいた情報かどうかを確認しないといけません。
特にあだ名や逸話については、後世に作られたものが多くあります。杉田玄白に関しても、確実な史料で確認できる情報と、伝説的な要素を含む情報を区別することが大切です。
同時代の史料に残る杉田玄白のあだ名
杉田玄白が実際に呼ばれていたあだ名は「玄白先生」「杉田先生」でした。書簡や記録から確認できる呼び方を詳しく紹介します。
弟子や翻訳仲間からの呼ばれ方
解体新書の翻訳仲間である前野良沢は、書簡の中で「玄白殿」と記しています。同じく翻訳に参加した中川淳庵も「杉田先生」という敬称を使っていました。
蘭学を学ぶ門下生たちからは「玄白先生」と呼ばれるのが一般的だったようです。師匠への敬意を込めた呼び方として定着していたと考えられます。
当時の学者同士では、字(あざな)で呼び合う習慣がありました。杉田玄白の字は「子鳳」であり、親しい間柄では「子鳳殿」と呼ばれることもあったのです。
患者や一般の人々からの呼ばれ方
江戸の町で診療を行っていた杉田玄白は、患者から「お医者様」と呼ばれていました。身分に関係なく診療する姿勢から、庶民にも慕われていたようです。
若狭小浜藩の藩医としての顔も持っていたため、藩内では「杉田先生」が一般的でした。藩主や家臣からは「杉田殿」と呼ばれることもあったと記録されています。
地域によっては「小浜の先生」という親しみを込めた呼び方もあったようです。出身地への郷土愛が感じられる素朴な呼び名といえます。
蘭学事始における自分の呼び方
杉田玄白が晩年に執筆した「蘭学事始」では、自分のことを「玄白」と記しています。自伝において、通称である「玄白」を一貫して使用していました。
著作の中では謙遜した表現が多く見られます。自分の功績を誇らず、むしろ翻訳作業の苦労や不完全さを正直に書いている点が特徴的です。
「やぶ医者」や「草葉の陰」といったあだ名は、蘭学事始に記載がありません。後世に作られた創作である可能性が高いと考えられています。
同時代の蘭学者・医師のあだ名と比較
杉田玄白と同時代に活躍した蘭学者や医師たちにも、さまざまなあだ名がありました。比較することで、当時の医師たちがどう呼ばれていたかがわかります。
前野良沢のあだ名
解体新書の翻訳に最も貢献した前野良沢は「蘭学の祖」と呼ばれています。オランダ語の知識では杉田玄白をしのぐ実力を持っていたためです。
良沢は「楽山」という号を持ち、学者仲間からは「楽山先生」と呼ばれていました。翻訳作業では中心的な役割を果たしながらも、表舞台には出ない控えめな人物だったといわれています。
名前を解体新書に載せることを辞退したエピソードから「陰の功労者」という呼び方もあります。完璧主義者ゆえに不完全な翻訳への署名を避けたのです。
中川淳庵のあだ名
解体新書の翻訳メンバーである中川淳庵は「本草学の達人」と呼ばれていました。薬学や植物学に精通していたことから付いたあだ名です。
淳庵は「淳庵先生」という通称で親しまれていました。蘭学だけでなく漢方医学にも詳しく、両方の知識を活かした治療が評判だったようです。
オランダ語の通訳としての能力も高く、「蘭学の橋渡し役」という評価もありました。
大槻玄沢のあだ名
杉田玄白の弟子である大槻玄沢は「蘭学の継承者」と呼ばれています。師匠の教えを受け継ぎ、蘭学の発展に大きく貢献したためです。
玄沢の「玄」は師匠である杉田玄白から一字をもらったもの。「玄沢先生」「大槻先生」という敬称で呼ばれることが多かったようです。
蘭学塾「芝蘭堂」を開いたことから「芝蘭堂先生」という呼び方もありました。多くの蘭学者を育てた教育者としての顔を表しています。
江戸時代の医師に付けられたあだ名の特徴
江戸時代の医師たちには、現代のような個性的なあだ名は少なかったようです。「〇〇先生」「〇〇殿」という敬称が一般的でした。
特定のあだ名が付くのは、特別な功績や特徴があった場合に限られます。「名医」「やぶ医者」など、腕前を評価するあだ名が多く見られました。
杉田玄白に「蘭学の父」というあだ名が付いたのは明治時代以降のことです。同時代には、そこまで大げさなあだ名で呼ばれていた記録は残っていません。
| 人物名 | 同時代のあだ名 | 後世のあだ名 |
| 杉田玄白 | 玄白先生・杉田先生 | 蘭学の父 |
| 前野良沢 | 楽山先生 | 蘭学の祖 |
| 中川淳庵 | 淳庵先生 | 本草学の達人 |
| 大槻玄沢 | 玄沢先生 | 蘭学の継承者 |
杉田玄白の本名・字・号とは?

杉田玄白の名前について、江戸時代の複雑なルールを踏まえて詳しく解説します。
本名「翼(たすく)」
杉田玄白の本名(諱)は「翼(たすく)」です。諱とは本当の名前のことで、親しい人や目上の人だけが呼ぶことができる特別な名前でした。普段の生活では滅多に使われることがありません。
字「玄白(げんぱく)」
杉田玄白の字(あざな)は「子鳳(しほう)」です。字とは、成人男性が正式な場面で使用する名前で、特に文書での署名で用いられました。
「子鳳」の「鳳」は鳳凰を意味し、高貴で縁起の良い鳥とされています。中国の古典文化では、鳳凰は聖人が現れる時に姿を現すとされる神聖な鳥です。
「鳳」という字からも、杉田玄白が自分に高い理想を課していたことが伺えます。
号「九幸(きゅうこう)」
杉田玄白は複数の号を使い分けていました。号とは、文人や学者が作品に署名する際に用いる雅号です。
最も有名な号は「九幸(きゅうこう)」です。「九」は中国思想では最高の数字とされ、「幸」は幸福や成功を意味します。医師として多くの人を救い、幸せをもたらしたいという願いが込められています。
もう一つの重要な号が「鷧斎(いつさい)」です。鷧は想像上の鳥の名前で、知恵と学問を象徴するとされています。「斎」は書斎や勉強部屋を意味し、学者としての矜持を表しています。
幼名「佐平次(さへいじ)」
杉田玄白の幼名は「佐平次(さへいじ)」でした。幼名とは、元服するまで使われる子供時代の名前です。
江戸時代では、男子は15歳前後で元服の儀式を行い、幼名から正式な名前に変わるのが習慣でした。
杉田家は代々医師の家系だったため、佐平次という幼名に将来は医師として活躍できるよう願いが込められていたと考えられます。
通称「玄白(げんぱく)」
杉田玄白の通称は「玄白」です。通称とは、日常生活で使用される名前のことです。医師として活動する際、患者や同僚からは「玄白先生」と呼ばれていました。
杉田玄白の別のあだ名一覧
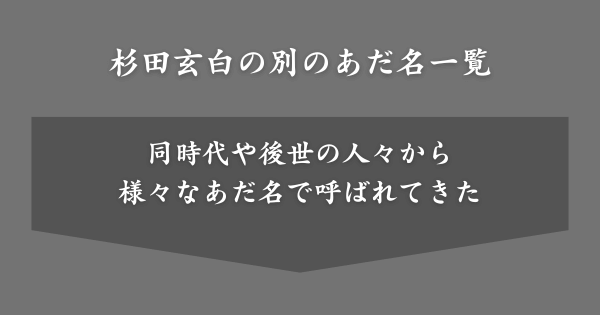
杉田玄白は長い生涯を通じて、同時代や後世の人々から様々なあだ名で呼ばれてきました。これまで付けられた杉田玄白のあだ名を、下記の表にまとめました。
| カテゴリ | あだ名 | 意味・由来 |
| 蘭学関連 | 蘭学の父 | 日本に本格的な西洋医学を導入し、蘭学発展の基礎を築いた功績から生まれた最も権威あるあだ名。明治時代以降に定着し、現在でも歴史教科書や学術書で使用される |
| 解体新書の翻訳者 | オランダの医学書「ターヘル・アナトミア」を「解体新書」として翻訳した業績を称えた呼び方。4年の歳月をかけた困難な翻訳作業は日本医学史上最も重要な出来事とされる | |
| 西洋医学の先駆者 | 漢方医学が主流だった保守的な医学界に風穴を開いた革新性を評価。実際の人体解剖を見学し、西洋医学の正確さに驚愕して導入を決意した先見性から | |
| オランダ学の開拓者 | 医学以外にも天文学、物理学、化学などの西洋科学全般に関心を持ち、蘭学普及に貢献。幅広い分野での知識欲と探究心を表した呼び方 | |
| 医師として | 名医 | 西洋医学の知識を取り入れることで従来の治療法では治せなかった病気の治療に成功。同時代の患者や同僚医師から高い評価を受けた実力を示すあだ名 |
| 町医者の星 | 身分の高い武士だけでなく一般の町人の治療も積極的に行い、庶民にも親しまれた医師だったことから。階級社会の中で平等な医療を提供した人格を表す | |
| 外科の名手 | 解剖学的知識を実際の手術に活かし、当時の日本では限られていた外科手術を西洋医学の知識により高度化。実践的な医療技術の高さを評価した呼び方 | |
| 人格・性格 | 勉強家 | 60歳を過ぎてからもオランダ語の勉強を続け、新しい医学知識の習得に励んだ生涯学習の姿勢から。年齢に関係なく学び続ける意欲を称えたあだ名 |
| 好学の人 | 医学だけでなく様々な分野の西洋科学に興味を示し、常に新しい知識を求める探究心から。学問への飽くなき情熱と好奇心を表現した呼び方 | |
| 温厚な先生 | 弟子や患者に対する優しい人柄と思いやりある指導から。厳しい指導をしながらも常に相手の立場に立って考える温かい性格を評価したあだ名 | |
| 謙虚な学者 | 「蘭学事始」で自分の功績を誇ることなく、むしろ苦労や不完全さを率直に記述した控えめな人格から。成功を誇らない謙遜の美徳を表す | |
| 探究心の塊 | 新しい知識に対する飽くなき好奇心と、困難を乗り越えてでも真理を探求しようとする強い意志から。学問に対する情熱的な姿勢を表現した呼び方 | |
| 社会的影響 | 時代の先駆者 | 江戸時代後期の社会変革に大きな影響を与え、西洋文明への扉を開く役割を果たしたことから。保守的な社会に新しい価値観をもたらした先見性を評価 |
| 開明思想家 | 古い慣習にとらわれず新しい知識を積極的に取り入れた革新的思考から。伝統的な価値観に挑戦し、進歩的な考え方を持っていた姿勢を表す | |
| 文明開化の先導者 | 明治維新後の文明開化につながる思想的基盤を作ったことから。西洋科学の重要性を早くから認識し、近代化の礎を築いた功績を評価したあだ名 | |
| 弟子・同僚から | 玄白先生 | 医学を学ぶ弟子たちが師匠に対する敬意を込めて使用した最も親しみやすい呼び方。厳しくも温かい指導者として慕われていたことを示す |
| 蘭学の師匠 | 前野良沢、中川淳庵らとともに蘭学発展の中心人物として、多くの優秀な蘭学者を育てた指導力から。門下からは日本の近代化に貢献する人材が多数輩出 | |
| 翻訳の名人 | 辞書もない時代にオランダ語から日本語への困難な翻訳を推理と努力で完成させた卓越した技術力から。言語的才能と忍耐力を評価した呼び方 | |
| 現代の評価 | 日本近代医学の恩人 | 現代の医学界から与えられた最高の評価。杉田玄白がいなければ日本の医学発展は大幅に遅れていたという認識から生まれた感謝を込めたあだ名 |
| 科学的思考の導入者 | 経験と観察に基づく実証的な研究方法を日本に紹介したことから。それまでの理論重視から実践重視への転換をもたらした功績を評価 | |
| 国際的視野の持ち主 | 鎖国時代にありながら世界の知識に目を向けた先見性から。閉鎖的な社会の中で国際的な視点を持ち続けた開放的な思考を評価したあだ名 | |
| 教育者としての偉人 | 単なる研究者ではなく多くの弟子を育て、知識の普及に努めた教育的功績から。学問の発展には後進の育成が重要という認識を持っていた姿勢を評価 | |
| 地域での呼び方 | 小浜の先生 | 出身地である若狭小浜藩への郷土愛と、江戸の人々が地方出身者に対して抱く親しみを込めた表現。故郷を大切にする人柄も慕われた理由の一つ |
| お医者様 | 住んでいた地域で身分に関係なく患者を診療する姿勢が地域住民に愛されたことから。庶民からの素朴な敬愛と感謝の気持ちを表した親しみやすい呼び方 |
杉田玄白に関してよくある質問
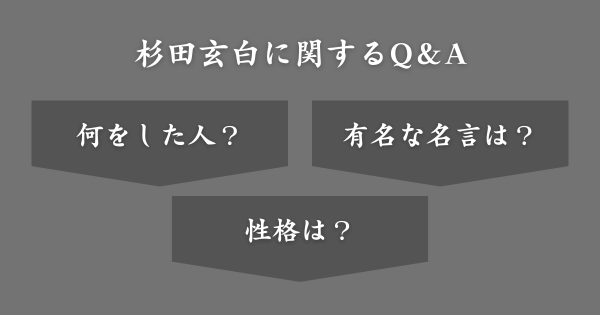
杉田玄白の功績や名言、性格について、わかりやすく解説します。基本情報を知ることで、なぜ杉田玄白が様々なあだ名で呼ばれるようになったのかが理解できるはずです。
杉田玄白は何をした人?
杉田玄白の最も有名な功績は、オランダの医学書「ターヘル・アナトミア」を日本語に翻訳したことです。翻訳作業は1771年から開始され、4年の歳月をかけて「解体新書」が完成しました。
体の正確な構造が初めて日本語で記述された解体新書により、日本の医学は飛躍的な進歩を遂げることになります。
杉田玄白は医師としても優秀でした。若狭小浜藩の藩医として働きながら、江戸でも多くの患者を診療していました。
西洋医学の知識を実際の治療に活かし、従来では治せなかった病気の治療に成功することも多かったのです。
また、教育者としての顔も持っていました。多くの弟子を育て、蘭学の普及に努めました。杉田玄白の門下からは、後に日本の近代化に大きく貢献する人材が多数輩出されています。
杉田玄白の有名な名言は?
杉田玄白の最も有名な名言は、「昨日の非は悔恨すべからず、明日これを念慮すべし」です。
「昨日の失敗を後悔するのではなく、明日同じ失敗を繰り返さないように気をつけなさい」という意味です。実際、著書『蘭学事始』に記されており、杉田玄白の座右の銘として知られています。
また、「昨日の非は、恨悔すべからず」という名言もあります。
意味はほとんど同じで、「過去の失敗を後悔するのではなく、未来に目を向けなさい」と言っています。杉田玄白の提唱している健康法「養生七不可」の中で記されている言葉です。
杉田玄白は蘭学を日本に広めた功績だけでなく、博識と健康意識の高さでも知られています。現代を生きる私たちにも、多くの示唆を与えてくれました。
杉田玄白の性格は?
杉田玄白は非常に勤勉で探究心旺盛な性格でした。60歳を過ぎてもオランダ語の学習を続けている上、「蘭学事始」を見ても杉田玄白の謙虚な人柄がよくわかります。
同時に、非常に好奇心が強い性格でもありました。医学だけでなく、天文学、物理学、化学など幅広い分野の西洋科学に興味を示していました。
患者や弟子に対しては、温厚で親切な人物だったそうです。身分に関係なく患者を診療し、弟子たちには厳しくも温かい指導を行っていました。
一方で、学問に対しては非常に厳格。いい加減な知識や推測による治療を嫌い、常に正確性を追求していました。
革新的な思考の持ち主でもあります。伝統的な漢方医学が主流だった時代に、西洋医学の価値を認め、積極的に取り入れたわけですからね。
【まとめ】杉田玄白のあだ名・本名
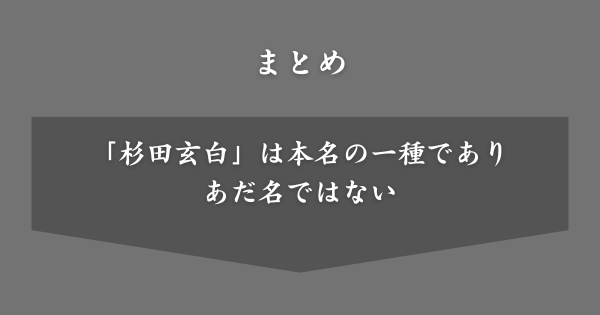
「杉田玄白」は本名の一種であり、あだ名ではありません。「玄白=やぶ医者」という意味も誤解です。
江戸時代の名前の付け方を理解することで、一人が複数の名前を持つ文化も見えてきます。
「蘭学の父」から「先生」まで、杉田玄白が様々なあだ名で呼ばれたのは、医師や教育者として多方面で活躍した証拠です。
名前やあだ名の切り口から歴史上の人物を知ることで、教科書ではわからない魅力を発見できます。杉田玄白だけではなく、ぜひ他の人物も探してみてください。









