最近では学校で「あだ名禁止」のルールが広がり、職場でもあだ名がハラスメント問題として取り上げられるケースが増えています。
あだ名と悪口の境界線は何か。いじめやハラスメントにならないために、私たちが知っておくべき判断基準とは何か。具体例とともに詳しく解説します。
- あだ名で呼ぶことはいじめ?
- あだ名がいじめになった事例
- あだ名がハラスメントになる?
- ハラスメントになった事例
- あだ名と悪口の境界線は?
- 陰で悪口のあだ名をつけていい?
あだ名で呼ぶことはいじめになる?

あだ名で呼ぶ行為は、状況や内容によって”いじめ”となります。本人が嫌がっているにも関わらず、継続的にあだ名で呼んでいる場合、法的にもいじめと認定される可能性が高いです。
特に学校では、あだ名が原因で深刻ないじめに発展する事例が後を絶ちません。
いじめの法的定義
いじめ防止対策推進法では、いじめを下記のように定義しています。
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為」
あだ名で呼ぶ行為は、「心理的な影響を与える行為」に該当する可能性が高いです。特に外見をバカにするようなあだ名は、被害者に精神的苦痛を与えます。
いじめを強める要素
いじめと判断される要素として、「継続性」と「集団性」があります。
一度だけ呼ばれたあだ名であれば、いじめには該当せず、軽い問題として処理されることが多いです。しかし、繰り返し呼ばれ続けることで、いじめ問題へと深刻化します。
複数の人が同じあだ名で呼ぶ状況も、被害者に強い孤立感を与えるため、いじめになる可能性が高いです。逃げ場がない状況を作り出し、学校生活を苦痛なものにします。
被害者の心理的影響
あだ名によるいじめは、被害者の自尊心に深い傷を与えます。特に思春期の子どもにとって、外見や能力を否定されることは、人格形成に大きな影響を及ぼすのです。
不登校や学習意欲の低下、対人関係への不安など、様々な二次的問題を引き起こします。大人になってからも、人との関わり方に影響するケースも少なくありません。
被害者が「大ごとにしたくない」という心理から、誰かに相談を躊躇することも問題です。我慢強い子ほど一人で抱え込んでしまい、周りが気づいた時には深刻化しているケースが多くあります。
加害者側の問題
あだ名でいじめを行う加害者の多くは、自分の行為がいじめであると認識していません。「親しみを込めて呼んでいる」「冗談のつもりだった」と弁明するケースがほとんどです。
しかし、被害者の気持ちを理解できない、もしくは理解しようとしない姿勢こそが問題の本質といえます。相手の立場に立って考えられないことが、いじめをする要因になっているのです。
学校や家庭での教育において、あだ名の影響力について正しく教える必要があります。言葉の暴力についての理解を深めることが、いじめ防止の第一歩となるはずです。
あだ名で呼ぶことでいじめになった事例
あだ名が悪口となり、学校で大きな問題に発展した事例は全国で報告されています。実際に学校でいじめ問題となった事例を紹介します。
さいたま市立小学校のいじめ
2022年、さいたま市の小学校であだ名に関する問題が起こりました。児童が体型を揶揄するあだ名で呼ばれ、不登校になったことがきっかけです。
被害児童は「デブ」を含むあだ名で毎日からかわれていました。担任教師が指導しても、休み時間に悪口が繰り返される状況が続いたのです。学校側は全校集会で注意喚起を行い、「さん付け」ルールを導入しました。
この事例を受け、さいたま市教育委員会はあだ名指導のガイドラインを策定しています。本人が嫌がるあだ名は悪口と同等であり、いじめ認定の対象になると明記されました。
静岡県立高校でのSNSいじめ
2021年、静岡県の県立高校でSNSを通じたいじめが発覚しました。クラスのLINEグループ内で、特定の生徒を侮辱的なあだ名で呼ぶ行為が横行していたのです。
被害生徒は「キモ男」「ぼっち君」などのあだ名で呼ばれていました。悪口のスクリーンショットが拡散され、他クラスにまで広がる事態となっています。保護者からの相談で学校側が把握し、いじめとして正式に認定されました。
加害生徒らは謹慎処分を受け、被害生徒への謝罪が行われています。SNS上のあだ名は証拠が残りやすい反面、削除が困難という特徴があります。この事件は県内の学校に通達され、SNS利用指導の強化につながりました。
大阪市立中学校の集団いじめ
2020年、大阪市の中学校で集団によるいじめが問題化しました。特定の女子生徒を容姿に関するあだ名で呼ぶ行為が、学年全体に広がっていたのです。
被害生徒は「ブス子」というあだ名を1年以上にわたって使われていました。本人が教師に相談しても「気にしすぎ」と軽視された経緯があります。保護者が教育委員会に申し立てたことで、ようやく調査が開始されました。
第三者委員会はあだ名による人格攻撃をいじめと認定しています。学校側の初動対応の遅れも指摘され、再発防止策の策定が命じられました。この事例は、あだ名が悪口として機能した典型的なケースです。
あだ名で呼ぶことはハラスメントになる?

相手が不快に感じるあだ名で呼び続ける行為は、ハラスメントに該当します。特に職場や学校でのあだ名は、深刻な問題です。
近年、働き方改革や人権意識の高まりと共に、あだ名によるハラスメントがより注目されています。
職場でのハラスメント問題
職場でのあだ名ハラスメントは、パワハラやセクハラの一つとされています。上司が部下を見た目や能力に関するあだ名で呼ぶ行為は、典型的なパワハラ事例です。
「出来損ない」「のろま」などの特徴を表すあだ名は、人格否定につながる可能性が高いです。職場の雰囲気を悪化させ、被害者の業務遂行能力にも悪影響を与えます。
女性の外見から付けたあだ名は、セクハラと判断される可能性が高いです。体型や容姿に関する呼び方は、性的な羞恥心を侵害する行為として問題視されます。
男性同士であっても、性的な意味のあるあだ名は適切ではありません。LGBTQへの配慮という観点からも、性別に関わる表現は避けるべきです。
学校でのハラスメント問題
教師が生徒に対して不適切なあだ名を使用することは、教育上の重大な問題です。指導的立場にある教師の言動は、生徒の人格形成に大きな影響を与えます。
生徒間でのあだ名についても、学校側には適切な指導を行う責任があります。放置してしまうと、深刻なハラスメント問題に発展する可能性が高いです。
部活動においても、先輩後輩の関係を利用したあだ名の強要は問題となります。体育会系の伝統という名目であっても、人権侵害は正当化されません。
あだ名で呼ぶことでハラスメントになった事例
職場であだ名を使用する行為が「パワハラ・セクハラ」と認定された事例がいくつもあります。実際の職場で問題となった事例を確認していきましょう。
大手IT企業でのパワハラ
2021年、大手IT企業で上司によるあだ名がパワハラ認定されました。部下を「ポンコツ」「使えない君」と呼び続けたことが問題視されたのです。
被害社員は人事部に相談し、社内調査が実施されました。上司は「親しみを込めていた」と弁明しましたが、本人が不快に感じていた時点で悪口と同等と判断されています。結果として上司は降格処分を受け、被害社員への公式謝罪が行われました。
この事例では、あだ名による継続的な人格否定がパワハラの核心と認定されています。業務指導の範囲を超えた侮辱的表現は、たとえ冗談でも許されないことが示されました。
地方銀行でのセクハラ
2022年、地方銀行の支店で女性行員へのあだ名がセクハラ認定されました。男性上司が「お局様」「おばさん」と呼んでいたことが問題となったのです。
被害女性は40代で、年齢に関する悪口を日常的に受けていました。「早く結婚しろ」という発言も伴っており、複合的なハラスメントと判断されています。社内のコンプライアンス委員会が調査を行い、上司は厳重注意処分となりました。
この事例は、年齢や容姿に関するあだ名がセクハラに該当することを示しています。被害女性は異動を希望し、会社側も認める対応を取りました。
製造業大手での懲戒解雇
2023年、製造業大手の工場で、あだ名のハラスメントによる懲戒解雇が行われました。特定の外国人従業員を差別的なあだ名で呼び続けた社員が処分されたのです。
加害社員は「〇〇人」という国籍を揶揄するあだ名を使用していました。被害者が上司に相談したことで発覚し、社内調査が開始されています。会社側は人種差別的な悪口と認定し、就業規則に基づく懲戒解雇を決定しました。
この事例では、あだ名が差別的言動に該当すると判断されています。外国人労働者の増加に伴い、同様の問題は今後も増加が予想されます。
あだ名と悪口の境界線とは?

あだ名と悪口の境界線は、相手の「感情・関係性・内容・状況」という4つの要素で判断できます。各要素がいくつ当てはまるかで、同じあだ名でも受け取り方が大きく変わるのです。
良好な人間関係を築くためにも、明確な判断基準を知っておきましょう。
要素1:相手の感情
「本人が嫌だと思ったら悪口」という基準は、最も重要な判断材料です。相手の気持ちを無視したあだ名は、どんなに親しみを込めたつもりでも悪口になります。
しかし、本人が「嫌だ」と言えない状況も多いです。立場の違いや性格的な要因で、はっきりと拒否できない場合があります。
そのため、呼ぶ側は相手の表情や態度から、本当に受け入れられているかを読み取らないといけません。言葉に出さなくても、不快感は何らかの形で現れます。
相手が笑顔でいても、愛想笑いである可能性を考えることが大切です。特に職場や学校などの上下関係がある場では、より慎重な判断が求められます。
要素2:相手との関係性
同じあだ名でも、親友から呼ばれるのと初対面の人から呼ばれるのでは、受け取り方が全く異なります。信頼関係の深さが、あだ名を受け入れられるかを大きく左右するのです。
長い付き合いであれば、多少からかいの要素があっても理解してもらいやすいです。共通の思い出や経験が、特別な意味のあだ名になることもあります。
一方、まだ関係が浅い相手のあだ名には気をつけないといけません。相手のことをよく知らない状態でのあだ名は、軽率な行為として受け取られる可能性が高いです。
人との距離感がおかしい人からのあだ名も、相手に不快感や恐怖感を与える可能性があります。空気を読んだり、相手の気持ちを察したりする能力が不足しているためです。
要素3:あだ名の内容
あだ名の内容自体も、悪口かどうかを決める重要な要素です。見た目の特徴をネガティブに表現したものは、明らかに悪口に該当します。
外見に関するあだ名は、特に注意しないといけません。相手がコンプレックスに感じている部分を示すあだ名は、深刻な心の傷を与える可能性があります。
相手の能力や性格を否定するようなあだ名も、悪口になりかねません。「のろま」「ばか」などの能力を否定する表現は、人格否定につながります。
逆に、相手の長所や愛らしい特徴を示すあだ名は、好意的に受け取られやすいものです。ただし、ポジティブな特徴でも本人が気にしている場合は、例外です。
要素4:使用される状況
あだ名が使用される場面も、悪口かどうかの判断に影響します。公の場とプライベートだと、あだ名の意味合いは同じではありません。
大勢の前で呼ばれるあだ名は、恥ずかしさや屈辱感を与える可能性があります。特に相手が納得できないあだ名の場合、公開処刑のような効果を持ってしまうのです。
職場や学校では、より慎重にあだ名を決めないといけません。プライベートでは問題ないあだ名でも、公的な場面では不適切と判断される場合があります。
緊急時や真剣な場面でのあだ名も、状況に応じて使用すべきかどうかの判断が変わります。場の雰囲気を読んで、適切な選択をすることが重要です。
陰で悪口のようなあだ名をつけるのはいい?

陰でのあだ名付けは、道徳的にも社会的にもおすすめしません。たとえ本人に直接害が及ばないとしても、結果的に人間関係へ悪影響を与える可能性が高いです。
周りへの悪影響
陰でつけられたあだ名は、必ずと言っていいほど本人の耳に入ると思ってください。もし伝わった時の本人の気持ちは、裏切られた失望感で満たされます。
一度失った信頼関係を修復することは、非常に難しいです。特に、職場や学校など長期間いる環境では、その後の関係性に大きな支障をきたします。
陰口を言っていた人に対する見方も大きく変わってしまいます。「表面では良い顔をして、裏では何を言っているかわからない人」という悪い評価が定着してしまうのです。
本人だけでなく、陰口を聞いていた人たちにも不信感が芽生えます。「自分も同じように陰で言われているかも」と思われる可能性も高いです。
行為者自身への悪影響
陰であだ名をつける行為は、自身の人格に悪い影響を与えます。周りの人は、普段の行為を通して人間性を判断するものです。
「陰口を言う人」というレッテルは、一度貼られると払拭するのが難しいです。将来的なキャリアや人間関係において、大きな傷になる可能性があります。
自分自身の精神的な成長が止まってしまうリスクもあります。他人を貶めることでしか自己肯定感を得られない状況は、健全な人格形成の妨げです。
社会人としての信頼性や評価にも悪影響になり得ます。責任ある立場に就く際の判断材料として、日頃の姿勢が重視されるためです。
あだ名の法的リスク
職場でのあだ名が原因で、名誉毀損や侮辱罪に問われる可能性もあります。特に、録音や文書として記録が残っている場合、法的な問題に発展するリスクが高いです。
企業においては、就業規則違反として懲戒処分の対象となる場合もあります。ハラスメント防止の観点から、厳しい処罰を課す企業が増えているのが現状です。
学校でも、いじめ防止対策の一環として厳しい指導が行われています。陰でのあだ名付けが発覚した場合、反省文や停学などの重い処分を受けることもあります。
SNS上では、より広い範囲に拡散される危険性があるため、注意しないといけません。デジタルタトゥーとして残り続け、将来にわたって問題となるのです。
【まとめ】あだ名と悪口
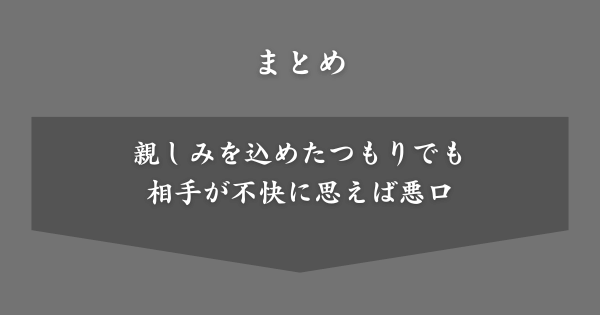
あだ名か悪口かの境界線は、「相手の感情」「相手との関係性」「あだ名の内容」「使用される状況」によって決まります。
その中で最も重要なのは、相手がどう感じるかです。親しみを込めたつもりでも、相手が不快に思えば悪口となってしまいます。
いじめやハラスメントを防ぐためには、適切な距離感を保ち、相手の気持ちを察する力を身につけることが不可欠です。
陰でのあだ名付けは、信頼関係を壊すリスクがあるため、絶対に避けましょう。相手への思いやりと敬意を持って関わることが、信頼関係を築く鍵になるのです。







